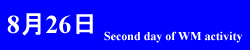
本日の活動内容
今日の午前中は実際にコンポストを行っている方々を招いてミーティング・・・の予定だったのですが、
急遽コンポストを行っている家庭を訪問して直にコンポストを行っている様子を拝見する、
という嬉しいハプニングが!!
と、いうことで、回ってきました実際に。
まずは一軒目、binコンポストを行っているお宅に訪問。
 |
家の奥地(?)に潜入。 |
これがbinコンポスト 。実際に使われているのを見るのは初めてです。 ちなみに、隣に写っている麻袋も コンポストの一種です。 |
 |
このお宅では、一日一回、夜に生ゴミを入れているそうです。
binコンポストに使われている微生物が含まれた液体は、
日本でよく使われているボカシや米ぬかと同じように、脱臭、防虫の効果があるらしいです。
Effective Micro-organismってやつですね。略してEMです。他には、やっぱり灰などが使われているようです。
このコンポストは、およそ3ヶ月で堆肥が使用できるらしいのですが、
隣で行われている、麻(?)袋を使ってのコンポストは、堆肥が出来上がるまでにおよそ3〜6ヶ月かかるらしいです、
同じ微生物を使っていても、かなり大きな差が生じてしまっているようです。
・・・これ、なんだろう |
実はこの写真、ネパールのWaste managementを語る上で非常に重要な光景だったらしいです。
ネパールのゴミ回収のシステムとして、市が回収するパターン、有料業者が回収するパターン、
そしてそのままゴミを投棄するパターンがあるらしいです。これは、そのなかで有料業者に頼むときに、こうやってゴミを吊るしておくらしいです。
次は、何て言えば・・・仮に、レンガコンポストとします。
まず、実際に見てください。
本当に今回は初めてづくしです。 このコンポスト、非常に農業くさいです。 基本的に、大きな庭がないとできないんです。 |
 |
これから回った家庭の多くは、このコンポストをメインに行っていました。
搾取できる堆肥の量と、循環効率が他の携帯用コンポストに比べて抜群に良いです。
やはり、堆肥を育てるには土の中ですね。
まぁ、なかなか日本で実行できるものではないんですけど。
基本的な構造は、ネパールで行われているミミズコンポストと同様です。
敷居を二つに分け、片方づつ交互に使用していきます。
片方でコンポストを行い、溜まったらもう片方ひっくり返すと、既に出来上がった堆肥から使用することができます。
下のほうで微生物が行き来できるため、次に隣でコンポストを行う場合に、
成長した微生物が使用でき、時間の短縮ができます。
ただ、コンポストを放置しすぎると、できた堆肥が土に変わってしまいます。
現在、WISDで実験中のコンポストもいくつかあります。
その中のひとつとして、地面に紙や草類を蒔いて、その中にミミズを放ち、
ミミズが分解してくれるかどうかを試すものや、Binコンポストが外でできるかなど、
まだまだ改善の余地がありそうです。ちなみに、Binコンポストを外で行った場合、
雨水を避ける必要があったり虫が入って微生物が食われるなど、効率は悪いが一応使えるらしいです。
最後に、コンポストの失敗例を見学しました。このコンポストはPitコンポストと呼ばれ、
深さ約2feetの穴にレンガを敷き、その中に生ごみを入れるという、いたってシンプルな構造です。
この方式は、奥にできた堆肥を取り出すといったことができないため、
上にかぶせた生ごみが全て堆肥に変わるまで使用することができません。そのため、堆肥として使用するまでに、
およそ4〜6ヶ月かかってしまいます。また、当時はコンポストが嫌気性だと考えられていたため、
微生物の培養も思うように行かなかったそうです。
これが(元)Pitコンポスト。 空気が足らず、微生物が育たなかったため、今、隣に焼却炉を建て、堆肥になりきれないものを燃やしているそうです。 |
|
他の屋外用コンポストと比べ、狭く、場所の移動ができないこと、
堆肥化のローテーションができないことなどが、問題点として挙がっています。
これらの今まで試した多くのコンポストから、風通しをよくする、水を避ける、
EMを使うといった改善方法が発案されていったそうです。
さっきから、ものっすごいコンポストばかり書いていたので、最後に、ネパールで行われていた祭りの様子なんかを・・・
 |
これは、クリシュナーという神様の誕生日を祝うお祭りらしいです。 |
ネパールでは、まだ階級制度が根強く残っているらしく、階層によって参加できるお祭りが変わってくるそうです。
日本人には、もう無い感覚だねぇ
午後の活動

午後1時過ぎー地域へのへのアンケーティングを開始する。
Mi-tech生の作った質問シートを
使って留学生とナショナルカレッジの学生に協力してもらいながら
小さな食品店を周る。戸惑いながら緊張の訪問が始まる。(^_^;

質問項目の英語訳はすべて後藤先生とブレンダ先生による「プロフェッサーズ・プロフェッショナル書き下ろし」
によって完璧に仕上がっている。
だが、地元の人の言語の力の面・項目の講読のみによる可能な質問内容の理解度の限界・時間短縮などから
急遽アンケート方式からインタビュー方式に変更する。
オキュペーションの質問、年齢からすべて手取り足取りのネパール語による説明が必要になった。
結局はワン・バイ・ワンのネパール語でのやりとりの方向に進んでしまったが、
あの状況では英語で口出しをすることなどは不可能であり、やはり仕方がなかったとしか言えないだろう。
結局「共同作業」と言うよりはほぼ「任せっきり」の状況であった (-_-;

インタビューの効率性を考慮してグループを二分割することに決まった(アスタの提案による)。
個人的にはこれにより一グループのリーダーとして一気に責任がかぶさってくる。
私のグループはアスタ・ジャスミン・ アシの三人が交代でインタビューを行ってくれる。

インタビューに行く途中に、ネパール人の宗教観についての話になった。
国民の信仰の割合について、家々の門構えにあるサイババの写真について、ヒンズー教の神について。
本日8月26日はクリシュナ神の生誕を祝う休日であり、この話もまた盛り上がった。
アスタたちによるとネパールでは神が一人ではいないため、
どちらかというと「ヒンズー教のすべての神」に対して祈りを捧げる人が多いらしい。
午後はダルバーツを食べてから、私たちの班は
コンポストを使う家に行きコンポストを配ってきました。
天気は晴れ!!
住宅地を歩いているとネパール人の生活もみることができました。
まわった家は、7件。
それぞれに環境問題への関心などのを聞くアンケートをしました。

外で遊んでいる子やふらふらしている子
コンポストに興味を持ってくれる子・・・・みんなのんびり生活しています。
訪問した家はどこも大きな家ばかり・・・意外にコンポストを使おうとしている
家庭が多いことに驚きました。
日本でもこんなにコンポストのuserは増えるのだろうか?
環境問題への関心はネパールでも確実に高まっていると感じました。
子供たちが遊んでいる環境はよいとはいえない。この子供たちのためにも
よい環境を作る必要がある。