
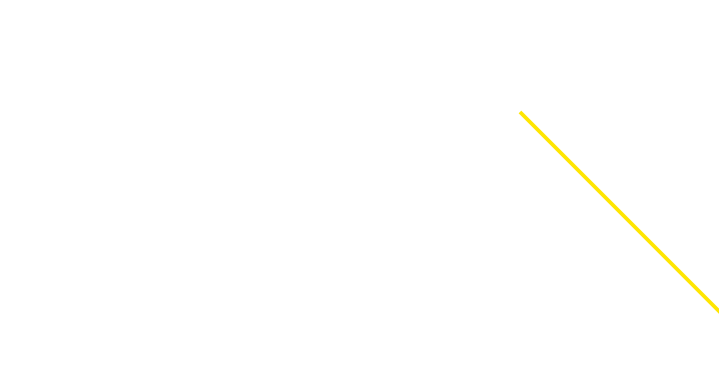


「探究」とは、高等学校で設けられている総合的な学習プログラム。
体験活動や人々との交流を通じて、日々の生活の中に潜むさまざまな課題を
見つけ出し、原因を考え、調べ、解決へと導く力を育てます。
東京都市大学では、探究学習が高校生の皆さんのより良い学びの機会になることを願い、
本学の教員・学生が探究学習に一緒に取り組む新しいカタチのイベントをスタートします。
社会が求める「課題発見・解決能力」「論理的思考力」「コミュニケーション能力」を身につけるとともに、
知識やアイデアを課題解決に役立てるおもしろさを一緒に体験しましょう。
探究学習イベント
OPEN MISSION
~あなたの気づきが、未来を動かす~
2025年12月25日
探究学習イベント「OPEN MISSION」
[ 2025年度スケジュール ]
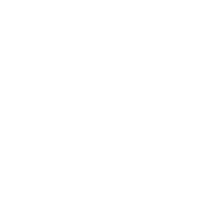
公開中のミッション動画を見て、「参加理由・課題計画(申込フォーム内に記入)」を5月21日(水)までに作成し、申込。その後、テーマ毎に【2】探究ワークまでの指示があります。
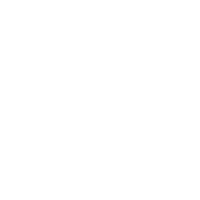
【1】で取り組んだミッション(宿題)について、教員もしくは研究室の学生から課題に関するレクチャー等を受け、内容を掘り下げます。
※テーマ「SDGsと科学技術」は、6月8日(日)の開催となります。
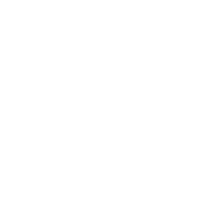
【2】探究ワークを受けて、8/5(火)に行われる【4】成果発表に向けて、「個人ワーク」「グループワーク」を実施。本学図書館利用や教員・学生からのアドバイスを受けることも可能です。(※1)
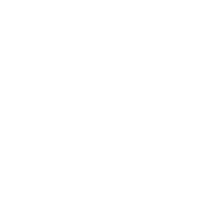
【1】~【3】で取り組んだ成果を発表。教員から評価コメントと修了証明書を発行。修了証明書は総合型選抜等で提出資料として利用できます。
[ 実施の様子(過去開催分)]




下記申込フォームからお申込みください。
お申込み開始:4/12(土)から
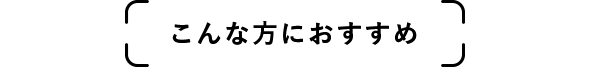
総合的な学習の時間で取り上げるテーマ選定の参考として、当ページの情報をご活用ください。また、当イベントは参加自由です。生徒の皆様のご参加もお待ちしています。
課題一覧に掲載されている内容を元に、授業で使用するテーマと課題を考える。
「教授の解説コメント」より、課題に取り組むにあたってのポイントや意義などを整理する。
当イベントに参加し、課題レポートの提出を求める。
List of issues